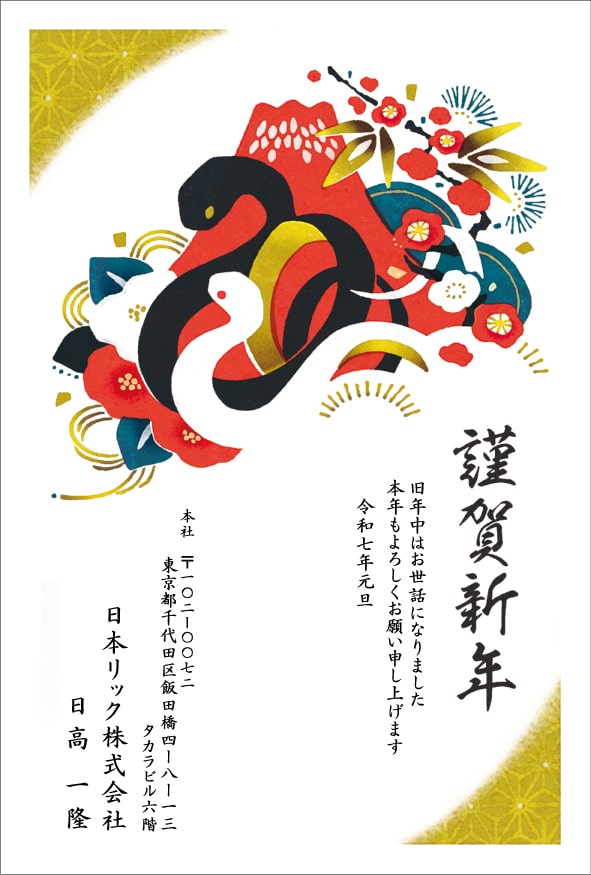先月末から半藤一利さんの「昭和史戦後編」を読んでいます。
この書籍はシリーズ化されており、最初に「昭和史1926-1945」、次に今回読んでいる「戦後編」、庶民の視点で描かれた「B面昭和史」、最後に「世界史のなかの昭和史」の順番で刊行されました。
私は「B面昭和史」を読んだ後、2番目に「昭和史戦後編」と刊行順とは異なる順番で読んでいます。半藤さんは、私と生まれ育った場所が近所でもあり、目に浮かぶような描写を、ご自身の経験から作家としての視点で描いてくれていて、大変興味深く読んでいます。
序盤の大半はGHQの占領や東京裁判といった戦後処理が続くのですが、その中でA級戦犯の一人「広田弘毅」についての記述があります。過去に城山三郎さんの「落日燃ゆ」を読んだことがあります。戦争阻止に尽力したにもかかわらず、一切の弁解せずに軍人達と共に処刑された広田の生涯を描いた作品であり、文官で唯一、戦争責任を取らされた悲劇的な人物と描写された作品であったと記憶しています。ところが「昭和史」で書かれた半藤さんの評価には若干の違いがあり、「人の評価は人によって違う」のを改めて感じています。
10月26日に介護事業部の全社研修「セミナーデー」を、全事業所をオンラインで繋いで実施しました。介護事業部は事業参入から20年が経過して18拠点となり、当初の20倍以上の売上になりました。一つひとつの事業所自体は小規模で、拠点を増やすことで事業を拡大してきました。
今年度の訪問介護事業所の倒産は、東京都だけで半年間で81件。その数は過去最高で多くは小規模事業所だそうです。コロナ禍で、無担保・無利子で猶予していた貸出の返済が始まり、更には介護保険料の改定が重なったことで、小規模事業所の運営が厳しくなってきています。今後の政策は企業を、大企業や成長企業に集約する方向にシフトしていくと思われます。当社としては事業所同士の情報交換や連携、祖業である人材ビジネスを含めた総力を結集して、成長を継続していかなくてはなりません。
介護事業所では、新卒の人と、その人から見ると祖父や祖母と同じくらいの年齢の人たちが同じ職場で仕事をする時代になりました。近い将来は訪問介護分野での技能実習生の就労も解禁になり、人材の多様化は更に進んでいくでしょう。
歴史上の人物は、様々な文献もあり色々な評価を目しますが、普段、仕事をする上で我々の場合はどうでしょうか?人材を事業の中心で展開する企業であっても人を評価する際に多方面で情報を集めることは、なかなかできません。従って少ない情報量で「あの人はこうだから~」といった判断をしたりします。特に日本人は否定的に物事を考え易いといわれいます。肯定的に人物を評価できれば人材の活用につながりますが、否定的に捉えると登用できなくなります。
組織の成長のためには、人を硬直的に評価することなく、色々な人たちと一体感のある職場環境を作っていく必要があると考えます。
日本リック株式会社
代表取締役 日高一隆